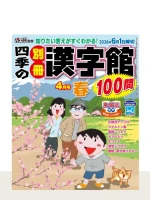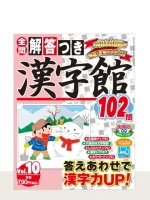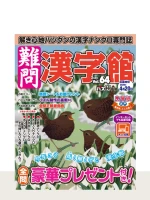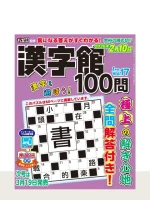熟語の特性、文字数から考える
第55話
今回は熟語の特性について書いてみようと思います。
4文字の熟語は基本的に「4文字の熟語が合体したもの」と「そうでないもの」に分けられます。
2文字の熟語の合体というと例えば「焼肉定食」、これについて私はトラウマがあります。
30年近く前、漢字ナンクロの妥当性を検証する際、参加していた事務所では「焼肉定食では文字が特定できない、煮魚定食だってなんだって、いくらでもあるんだから」という言葉が呪文のように飛び交っていたんです。
なぜ焼肉定食だったのか、それはいまもって謎なのですが(学校給食でもなんでもよいはずなので)まあおそらく、辞書に載っていないことと、どこか微笑ましい要素があったからだと思います(「辞書に載っている」という要素は妥当性に大きく関与しているのは事実なんですけど)。
なにはともあれ、2文字の熟語の合体としての4文字熟語はとても多いです。
それに対するのは正統的な四字熟語というか、故事成語由来というべきタイプのもの。「四面楚歌」「画竜点睛」の類いです。
ちなみに「四面楚歌」は楚の項羽が漢の高祖に包囲されたとき、周りを囲んでいる(四面の)漢軍のなかから楚の歌が聞こえてきて、楚の民がすでに漢に降伏しているのだと察して絶望した、という故事から来ています。
要するに、助けがもはやないこと・周囲が反対の者ばかりであること、の意味。
「画竜点睛」は絵の名人が竜の絵を描き、睛(目玉)を入れればたちまち竜が飛び去るから睛を描かなかったと言うと、人々がこれを疑い、無理やり睛を描きいれさせたところ、竜はたちまち天に登っていった、という故事に由来するそう。
つまり、ことを完成する際の最後の大切な仕上げを意味します。
また「瓜田李下」みたいなタイプもあります。
これはウリ畑で履物のヒモを直していたり、スモモの木の下で帽子を被り直していると、泥棒と疑われるから注意したほうがいい、という警句です。
疑わしい言動は日頃から慎むべき、という意味。これは2つのもの(瓜田と李下)が並列しています。
2つの並列というより対比のパターンもあります。「夏炉冬扇」などはそのタイプ。夏の火鉢・冬の団扇のように時節にあわぬ無用のものを例えています。
「南船北馬」も並列タイプ、南に船で北へ馬で行くいう意味。すなわち、絶えず各地を旅してるということです。
タイプは違えど、こうした四字熟語は歴史的に長いあいだ固定的に使用されることによって、そのもの単体で強固な意味を持つようになっています。
やはり「焼肉定食」とはひと味違いますね。私としてはナンクロで焼肉定食、ぜひ使ってみたいのですが(そうだ、焼・肉などを他の熟語で数回使用して、確定できるようにすれば問題ないわけですから、今度やってみたいと思います、笑)。
3文字の熟語というと、こちらも合体タイプが多いように思います。
それも2文字プラス1文字の。「○○家」「○○学」などがその代表格。
他にも、業・所・場・代などこのタイプはいくつもあります。
これらは漢字ナンクロ的に文字を確定する要素としてはあまり強固ではない、というのも想像しやすいと思います。
1文字プラス2文字という逆のパターンもあります。
「中学生」「亜熱帯」「悪感情」みたいなタイプ。
こちらは前者より数は少ないかもしれません、数えたわけではないのですが。
いずれにせよ、こちらも漢字ナンクロ的に文字を確定する要素としてはあまり強固ではありませんね。
強固な要素を持つ、変わったタイプの3文字熟語も分類しながらいくつかあげてみましょう。
まず類似・対比する独立した3文字を並列したタイプ、「真善美」「天地人」「素寒貧」「雪月花」「序破急」などがこれにあたります。
次に音に起因して当て字的に構成されるタイプとしては、「素寒貧」「安本丹」「珍紛漢」「頓珍漢」などが、そして起源に故事のようなものがあってそれが転じて意味が普遍化するようになったタイプ、中国や印度、宗教的なものに起源を持つものとしては「韋駄天」「伏魔殿」「有頂天」「金輪際」「修羅場」「未曾有」「南無三」「破天荒」、歌舞伎や博打に起因するものとしては「昼行灯」「外連味」「昼行灯」「出鱈目」などがあります。
「破魔矢」「注連縄」などは日本古来のもの、「金字塔」はピラミッドの翻訳、「飲兵衛」は江戸時代に洒落的に開発されたものだそう。
いろいろ面白いですね。
難読タイプとして「三和土」「十八番」などもあり、こちらは文字確定強度が高いです。
さて、お次は5文字。
実は5文字については先号(Vol.56)のコラムで「まっしろしろ」の流れで取り上げようとしたのですが、誌面が足らず今号に回したのです。
「まっしろしろ」はホワイトなので、意表をつくには5文字以上の熟語はとても便利、そういう流れで説明する予定でした。
今回、改めてそれをとりあげようとしたんですが、その前にまず3・4文字について書こうとして、またまた長くなってしまいました。
5文字について少しだけ触れておきます。
4文字よりさらに熟語の合体したパターンが多くなる5文字。そうでないのはあまり多くない印象です。
ふと思い出したものを並べると、「治国平天下」「入鉄砲出女」「三方一両損」とかでしょうか。うん?、これらも合体型かもしれませんね。
まあ「地球外生命」とは由緒というか歴史というか筋金が違いますけど。
さて、5文字と「まっしろしろ」について触りだけ少し。
まだチャレンジしたことはないのですが「日本国憲法」という熟語を「まっしろしろ」で扱うとします。
その時に、、、(続きは次号で)。